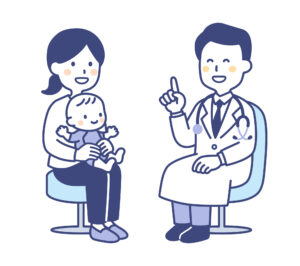「マスからレアへ」──製薬業界の変化と、私が感じる違和感とは?
Contents
🧭 「社会全体で支える」ということの意味を、私たちはどこまで考えているだろうか?
「フロモックス飲んどきゃ安心」──そんな時代が、かつてありました。
多くの人に、同じ薬が効く。薬は「マス」のためのものであり、製薬会社も「大勢の健康を守る存在」として信頼されていました。
でも今 1人あたり数千万円の医療費がかかるような「レア疾患」の薬に、巨額の保険料や税金が投下されています。私は医療の発展を喜びつつも、そこに「静かな違和感」を感じています。
今回は、製薬業界の過去と現在を見つめ直しながら、
「私たちは、誰のために、どこまで医療費を支えるのか?」という問いを投げかけてみたいと思います。
🧪 第1章:抗生物質の時代──薬が“みんなのもの”だった頃
1970〜2000年代、日本では感染症との戦いが大きなテーマでした。
その中で登場したのが、フロモックス、メイアクト、クラビットといった抗生物質。
これらの薬は、小さな子どもから高齢者まで、誰にでも処方され、風邪や中耳炎などで広く活用されました。
薬とは、「みんなのもの」であり、「手の届くところにある安心」だったのです。
しかも当時は、1製品で年間100億円以上の売上を叩き出す「ブロックバスター」が珍しくありませんでした。
製薬会社も、営業・医師・患者の“三方良し”のビジネスモデルで成長していた時代です。
🩺 第2章:生活習慣病との長い付き合い──“治す”から“管理する”医療へ
1990年代後半から2010年代は、生活習慣病が社会課題として台頭します。
- 高血圧 → オルメテックやアジルバなどのARB
- 高コレステロール → メバロチン、リピトール、クレストール
- 糖尿病 → DPP-4、SGLT2、GLP-1と新薬が次々登場
この時代、薬は「短期間で治す」から、「長期的にコントロールする」方向へ。
定期的な通院と服薬が必要になり、慢性疾患=継続的な売上の構図ができあがりました。
製薬会社にとっては、予防医療と継続治療という二本柱がビジネスの核となり、
国民にとっても「多くの人が少しずつ負担して、安心を得る」フェアな仕組みでした。
🧬 第3章:がん領域への挑戦──治療の進化と薬価の高騰
2000年代後半、製薬業界は「がん治療薬」へと大きく舵を切ります。
- リツキサン(リンパ腫)
- アバスチン(大腸がん)
- キートルーダ、オプジーボ(免疫チェックポイント阻害薬)
効果の高い新薬が登場する一方、薬価は1回数十万円〜数百万円に跳ね上がりました。
オプジーボが発売当初、年間治療費が3500万円を超えるとして社会問題になったのを覚えている方も多いでしょう。
この時代から、「効果があるならいくらでも払うのか?」「効く人と効かない人がいるのに?」という費用対効果の議論が医療政策の中でもクローズアップされ始めます。
🌍 第4章:難病・希少疾患への注力──“レア”な人々のために
ここ数年、製薬企業はこぞって「アンメット・メディカル・ニーズ(未充足の医療ニーズ)」にフォーカスしています。
たとえば:
- デュピクセント(重症アトピー性皮膚炎)
- アイリーア(加齢黄斑変性)
- 遺伝子治療、CAR-T(キムリアなど)
これらの薬剤は1人の命を救うことができるかもしれない。
でも、薬価は数百万円〜数千万円と高額で、対象患者数は少数。
ここで問題になるのが、「誰がその医療費を支えるのか?」という問いです。
🤔 第5章:違和感の正体──「マスがレアを支える構図」は持続可能か?
「ひと月の自己負担は8万円程度で済む」これは高額療養費制度の仕組みによるものです。
たとえ総額が1000万円でも、制度が差額を肩代わりしてくれます。
一見、これほど“優しい制度”はないように思えます。けれど、ちょっと待ってください。残りの992万円・・・ それ、誰が払ってるんでしょう?
答えは明確です。
あなた、私、みんなが「保険料」と「税金」で支えているのです。
📉「みんなで支える」の本当の意味を、私たちはどこまで理解しているのか?
病気になった人を、健康な人が支える。これは相互扶助の精神として極めて大切なことです。
しかし今の状況は、「一部のレアなケースに、マス(大多数)の財源が集中する構図」になっている。
それはまるで、ごく一部の乗客のために、全車両の運賃を3倍に値上げする列車のようなもの。
「納得感の喪失」こそが、制度の持続可能性を脅かす火種なのです。
💸 1人の治療費=5000万円。それが100人になったら?
仮に1人の難病治療に5000万円かかるとしましょう。今は対象者が少ないから、国全体で何とか吸収できています。
しかし──
- これが100人なら50億円
- 1000人なら500億円
- 万が一、適応が拡大すれば、数千億円の財源圧迫が生じます
財源は無限ではありません。医療だけではなく、年金、介護、教育、防衛にも割り振らなければならない。
🏛️ 医療の“正義”が、制度の“脆弱性”を覆い隠していないか?
「レアな人も救いたい」「差別してはならない」──これは誰しもが持つ当たり前の感情です。
でも一方で──
- 効果が確実ではない薬に数千万円を出す
- 1年生存が延びるかもしれないというエビデンスで薬価が付く
- その費用が、他の医療・教育・保育予算を圧迫する
こうした現実を前に、「感情だけで制度を運用することの危うさ」に、声を上げなければいけないと感じています。
🐜 たとえ話:蟻とキリンの話
ある日、働き蟻たちが一生懸命、食糧を集めて暮らしていました。そこへ、背の高いキリンがやってきて、こう言いました。
「ごめん、僕はこの葉っぱしか食べられないんだ。すごく高い場所にあるんだけど、取ってくれる?」
蟻たちはがんばって何度もよじ登り、重い葉を運びました。キリンは感謝し、満足して帰っていきました。
けれど、蟻の中にはこんな声も出始めました。
「ねぇ、それって本当に、ずっと続けるべきことなの?」
レアな状況にある人を支援することと、その“仕組み”が永続的に成立するかは、まったく別の問題なのです。
📊 海外ではどうしてるのか?
欧米諸国では「費用対効果」に基づく薬価評価制度がすでに導入されています。
たとえばイギリスのNICEでは:
- 1QALY(質調整生存年)あたりの費用が約3万ポンド(約600万円)を超えると、薬価の採用が難しくなります
つまり、「どんなに希少でも、高すぎる薬は認めない」判断をするのです。
⚠️ “このままでいい”という空気が一番危ない
制度が崩壊するとき、人は叫びません。声なき圧迫──それが最大の危機です。
気づかぬうちに保険料が上がり、医療控除が削られ、福祉が縮小される。誰もが損をして、でも誰も何が原因かわからない。
そんな“見えない損失”が、すでに始まっているのではないかと、私は感じています。
🔁 だから、問い続けたい。「誰のための医療か?」
高額医療が必要な方を否定したいのではありません。製薬企業の研究開発努力を軽視しているわけでもありません。
でも、「善意だけで設計された制度」は、いつか“逆に不平等”を生むかもしれないという危機感を、私たちはもっと持つべきです。
「この薬、誰のために、誰がどれだけ負担しているのか?」
この問いを避けずに向き合うことが、社会全体の“やさしさ”を持続可能にする唯一の道だと、私は信じています。
🧾 終章:問いを持つことは、誰かを否定することではない
難病の方が悪いわけではない。製薬企業が努力していることもわかっている。
でも、「このままでいいの?」という問いを持つことは、誰かを否定する行為ではないと思うのです。
むしろそれは、社会全体の“優しさを持続させる”ための問いだと私は信じています。
📌 最後に:私たちができる第一歩は「知ること」から
医療は、自分や家族の将来に必ず関わるものです。
そして、制度の維持には“無関心のコスト”が最も高くつきます。
だからこそ、今一度問い直したいのです。
「この薬、誰のためで、誰が支えているのか?」
一人ひとりが“知る”ことから、次の社会の在り方が見えてくるかもしれません。